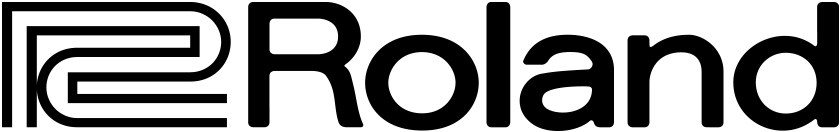コンセプト
SP-404、MKII、SXの当初の製品コンセプトと計画はどのようなものでしたか?
山田 : SP-404は当時定番となっていたSP-303の継承、SP-404SXではSP-404の継承に加えサンプル容量の拡大と音質の改善がコンセプトとなりました。
白土 : SP-404MKIIの初期の製品コンセプトは、SP-404のフォーマットとワークフローをキープすることです。それを維持しつつ、ユーザーがあっと驚くような劇的な進化を示すことを意識して開発を進めました。SP-404SXから12年がたっているので、豊富に蓄積されたユーザー・フィードバックを分析し、本当に重要なものを見定める必要がありました。すべてのアイデアを盛り込むと膨大になりすぎるため、山田さんに何度も相談しながら開発を進めました。また、SP-404SXによってビート・メイカーのSPユーザーがかなり増えたため、そこへのアンサーや恩返しとしてMKIIを出したいという思いも強く持っていました。
山田 : SP-404では表立っては言っていませんが、カスタマイズ要素を盛り込めないか、は密かに考えた案件です。
白土 : SP-404は、Lo-Fi Hip-Hopというイメージが強かったですが、SP-404MKIIは、もっと色々な音楽ジャンルの人に知ってもらいたい、使ってもらいたいという想いで開発をしました。音質やエフェクトもHouse/Technoやそれ以外の電子音楽にもマッチするように作られています。SP-404MKIIという楽器を通して、お客様が、今まで経験したことのない新しい文化や音楽に出会うきっかけになれば、嬉しい限りです。
導きの光
エンジニアとしてのキャリアにおいて、メンターは誰ですか?(Rolandあるいはそれ以外)
山田 : 入社後初めて開発部に配属された際の部長です。とても温かみのある人柄で開発をリードしていました。まだ若い私に色々なチャレンジの機会を与えてくれたり、製品開発において意見を求めてくれたり、開発における姿勢を最初に見せてくれた方です。
白土 : SP-404MKIIの開発中は、たくさんのメンターにお世話になりました。
中でも山田さんには様々な相談をしました。なぜSP-404のオリジナルではこのような設計になっているのか。それを変えても良いのか、変えるべきではないのかなど。彼が当時決めた仕様の一つ一つのストーリーを説明してくれたお陰で、変えても良い部分が明確になったことを覚えています。
また、SP-404MKII開発当時の部署の上司である山里さんや蓑輪さんにもたくさんのアドバイスを頂きました。企画の考え方やプロモーションの在り方、ビジネスの考え方など、当時の私にとっては非常に価値のあるアドバイスでした。
"SP-404の開発を通じて自分の音楽的興味が広がった気がします。"
Kenji Yamada
404の波に乗る
SP-404と現代のビートカルチャーにおけるその位置付けについてどう思いますか—これほどの人気を得ると思っていましたか?
山田 : 全く想像していませんでしたし、404dayとして皆さんが祝ってくれるなんて全くイメージになかったです。
白土 : 私がSP-404の存在を知った当時(2005年)、正直、これほどの人気を得ると思っていませんでした。世間では、DJの補助的なツールという認識があったと思います。
私がSP-404の新たなコミュニティを意識し始めたのは2010年頃だったと思います。当時、『remix』や『ele-king』といった日本の音楽雑誌がLow End TheoryやBrainfeederを特集し、それらの記事の中でSamiyam、Teebs、Ras G、TOKiMONSTAなど、SP-404を使っている海外アーティストの存在を知りました。 その当時、Low End Theoryは年に1-2回ほど日本でツアーをしていて、私は何度かそのイベントに足を運んでいました。中でも一番印象に残っているのは、2012年の代官山UNITでのRas Gのライブでした。中毒性のあるサイケデリックなビートに、Sun Raの楽曲からサンプリングした音が所々に散りばめられ、まるで宇宙空間にいるような感覚に陥りました。彼の神懸かったライブパフォーマンスの衝撃は、10年経った今でも私の脳裏に焼き付いています。このようなビートカルチャーが成長していく過程をリアルタイムに見れたことで、私の価値観が大きく変わりました。
影響と関心
あなた自身の音楽的興味は、SP-404の開発にどのような影響を与えましたか?
山田 : 影響的には逆で、SP-404の開発を通じて自分の音楽的興味が広がった気がします。私的には楽器とその発音原理に興味が強く、SP-404については「楽器として成り立つためには?」という視点を常に意識していたように思います。
白土 : 過去を遡ると、私が初めてローランドのSPシリーズに出会ったのは、1999年、私が高校生の時に行ったダンスホール・レゲエのイベントでした。当時、日本ではMighty Crownを中心としたジャパニーズ・レゲエが流行しており、ダンスホールやダブのセレクター(DJ)が、曲と曲の間に観客を盛り上げるためのツール(サイレン音やピストル音の再生マシン)として、サンプラー(SP-202/303)を使っていました。また、これは日本特有の使い方かもしれませんが、バラエティ番組や舞台演劇の効果音、ラジオのジングル等多岐に使われ、ワンショット・サンプラーのスタンダードになりつつありました。
2000年代、大学生だった私は、毎週のように地元(茨城県水戸市)にあるレコード店(Vinyl Machine)に通い、ダンスミュージックで使用されるサンプリングソースの知識を吸収することに生活の殆どの時間を費やしていました。当時はまだShazam(音楽検索アプリ)やDiscogs(オンライン音楽データベース)がなかったため、自らの足でレコード店とクラブを往復することで音楽に関する情報を収集し、日本の地方都市特有のジャンルレスなクラブカルチャーを体感することで様々な音楽から刺激を受けると共に、特にサンプリングをベースとしたHip Hopに非常に影響を受けました。
"過去を遡ると、私が初めてローランドのSPシリーズに出会ったのは、1999年、私が高校生の時に行ったダンスホール・レゲエのイベントでした。"
Takeo Shirato
白土:2000年代前半に、MadlibやJ DillaがSP-303のパワー・ユーザーであることを明らかにし、また、MadvillainのMadvilliany等Hip-Hopの金字塔となるアルバムがSP-303を中心に制作されていることを知った私は、SPのビートカルチャーに深くのめり込んでいきました。
SNS(インスタグラムなど)の発達により、SP-404(#SP404)を使ったカジュアルでインパクトのある投稿がここ5~6年で劇的に増加し、世界中でSPコミュニティが形成されていきました。また、サブカルチャー(アンダーグラウンド)からメインストリームに移り変わっていく過程をリアルタイムで見てきました。
フィードバックを掘り下げる
そのようなカルチャーから製品の開発に影響を受けましたか?
白土 : このように、SPシリーズは音楽シーンに多大な影響を与えてきましたし、私もその影響を非常に強く受けてきました。したがって、SP-404MKIIの開発者としての私の使命は、単に機能追加や使い勝手を向上させるだけでなく、SPが培ってきた歴史・文化を継承し、私自身の経験も生かして次世代のビートカルチャーに進化させることだと考えました。
私は、開発の初期段階で、世界中のSPコミュニティにあるほとんど全ての投稿をチェックしていきました。幸いにも、SPコミュニティは非常に活発で、次の新製品を期待した機能追加や改良の要望が投稿されていました。SP-404(2005年)の発売から16年経過していたこともあり、コミュニティには膨大な情報が存在していました。
私は、レコード店の棚の端から端までレコードを掘るように、ユーザーコミュニティでSPユーザーの要望をリストアップし、それを分析して、SP-404MKIIの製品仕様に落とし込んでいきました。
また、ピーター・ブラウン(プロダクト・プランニング・マネージャー)と協力して、SP-404のパワー・ユーザーに直接インタビューし、製品仕様の方向性に間違いがないことを何度も確認し、設計をスタートしました。これは難しいことではありませんでしたが、設計のスタート地点に辿り着くまでに多くの時間を費やしました。
"レコード店の棚の端から端までレコードを掘るように、ユーザーコミュニティでSPユーザーの要望をリストアップし、それを分析して、SP-404MKIIの製品仕様に落とし込んでいきました。"
Takeo Shirato
アーティストのSP-404の使い方で、驚いたことはありますか?
山田 : サンプルプレイバッカー的な用途が主になると想像していたのですが、思いの外、ドラムプレイ並みにパッドを叩いたり、積極的にEffectを使用してのリアルタイム性のあるパフォーマンスを見られるのは驚きの一つです。
白土 : 私は、週末にナイトクラブやライブハウスによく足を運んでいます。ある時、SP-404SXを2台とDJミキサーを使って、フェードイン/フェードアウトさせながら、楽曲を交互にミックスしているアーティスト(RAMZA、duenn)を見かけました。一般的に、SP-404SXを使ったDJミックスは、全てカットイン/カットアウトになってしまいます。しかし、彼らは、SPを複数台使ってより実験的なエレクトロニック・ミュージックをスムーズにミックスしており、私は彼らのアプローチからインスピレーションを受け、SP-404MKIIに搭載されたDJモードの発想に至りました。 また、SP-404は多用途サンプラーとして、特に日本で色々な使われ方をされています。 野球場のファウル等の警告音や選手入場曲、アイドルイベントの拍手や掛け声、ヒーローショウで悪役と戦う時の音、ホストクラブのシャンパンコール等、他にもたくさん。20年の間で様々なタイプのユーザーに使われ、そして、我々が想像もしていなかったような使われ方をされていることに日々驚きを感じております。
"20年の間で様々なタイプのユーザーに使われ、そして、我々が想像もしていなかったような使われ方をされていることに日々驚きを感じております。"
Takeo Shirato
アップデートで常に新鮮さを保つ
SP-404とその多くのアップデートについて、設計や生産プロセスで直面した最大の課題は何ですか?
山田 : 担当したSP-404、 SP-404SXについて、SP-404はSP-303と、SP-404SXはSP-404と、それぞれ同じ操作/フィーリングで同じ演奏表現ができる事が課題の一つでした。
白土 : SP-404MKIIでは、いかにコストを抑えつつ(SP-404SXとSP-404MKIIを同じ価格帯にして)、大きな進化を見せられるのかということが最大の課題でした。発売から16年も経っていたため、原材料の高騰は非常に大きな障壁となりました。これまでと全く同じ構成で設計したとしても、販売価格を上げざるを得ない状態になります。一つ一つ部品を見直し、システム構成も一新して、大幅なコストダウンを実現しました。パーツの採用に関してはさまざまなツテを頼りましたし、半導体メーカーの方とも相談を重ねました。SP-404MKIIでは有機ELディスプレイを採用しており、これも高価なパーツです。そこで、社内を駆け回って“この有機EL使いませんか?”と、私がサプライヤーのように別の製品担当へ売り込んだりもしました。あの手この手でコスト面を考慮していった結果、この価格帯を実現できました。
また、私自身の能力にも課題がありました。それは英語力です。SP-404MKIIの開発を始める前は、ほとんど英語を話すことができませんでした。しかし、今では私の最大のパートナーであるイタリア在住のソフトウェア・エンジニアと、最初は四苦八苦しながら英語でコミュニケーションをとり、何とか要素技術開発的にサンプラーの実験を重ねていきました。また、マーケティング担当はアーティスト(Recloose)としても活躍する海外メンバー(Matthew Chicoine)で、海を越えてさまざまなシナジーが生まれたことでSP-404MKIIを実現できました。
SP-404の発売以来、最もエキサイティングなアップデートは何だったと思いますか?
山田 : SP-404MKIIのリリースは私にとってエキサイティングな出来事でした。よもやSP-404後継機種が登場するとは想像していませんでしたし、SP-404/SP-404SXでは実現できなかった事、やりたかった事が可能になっています。
白土 : SP-404MKII発売後も定期的にメジャーアップデートを実施し、今も尚、進化を続けることです。 SP-404MKIIの発売後も、フィードバックを得るために、貪欲に世界中のユーザーとの直接対話を続け、そこから得られたアイデアをメジャーアップデートとして反映してきました。2022年7月にv2.0. 2023年4月にv3.0、2024年4月にv4.0、そして、2025年4月(現在)のv5.0。
そして、たくさんのコラボレーター(Stones Throw、 KDJ Records、 Koala、 Melodics、 Serato etc..)とも、一緒に開発を進めることができたことも非常にエキサイティングな経験でした。
ローランドと音楽サブカルチャー
SP-404のようにサブカルチャーを発展させているローランドの楽器は他にもありますか?
山田 : MC-303を最初とするgroove gear群は、テーブルトップ型の電子楽器を演奏するというカルチャーや、そういった楽器群が各社から登場するになった源流だったと思います。
白土 : 私にとっては、TR-808/TR-909/TB-303です。もはやサブカルチャーではありませんが、これらの製品がなければ、今日の全てのダンスミュージックカルチャーは存在していないでしょう。世界中でナイトクラブでは、毎週末のようにこれらの機材の音が、一晩中鳴り響き、世界中のオーディエンスがこれらの機材の音を浴びています。私の人生を振り返っても、これほどまで聴いた機材はないと思います。それと、RE-201です。ギターエフェクターとして使われるだけでなく、私の音楽人生の中で最も影響を受けたDUB MUSICにはなくてはならない機材となっています。RE-201がサブカルチャーを直接生み出したり、発展させたわけではありませんが、様々な音楽ジャンルにとってなくてはならないものになっています。
アドバイスと実績
楽器エンジニアを目指す人にアドバイスをするとしたら、それは何ですか ?
山田 : 楽器を作ることがゴールではなく、それを使うお客様が楽器を演奏して楽しみを得る、それを聴く方々がハッピーになれることが大事。様々な方々との対話を行なってその延長線にゴールを持つことがポイントだと思います。
白土 : 一番重要なことは、音楽やその背景にある文化、その音楽や文化に関わる人に興味を持つことだと思います。そして、その次に、その方たちとコミュニケーションを取って、多様な価値観を理解し、そこから生まれる新たなアイデアを形(楽器を開発する)にする力を身につけることだと思います。
他に開発したローランドの楽器で、誇りに思っているものは何ですか?
山田 : Fantom-S seriesです。サンプリングをいかにワークステーションに取り入れ、お客様に使って頂くか、開発チームで議論を重ねながら開発した製品です。
白土 : 2019年に発売したFANTOMです。私がローランドに入社して最初の製品です。私は、それ以前は、インクジェット・プリンターやデジタルカメラのハードウェアやFPGAのエンジニアをしていました。FANTOMは、ワークステーションタイプの多機能シンセサイザーとして、複数のカスタムチップと追加チップを組み込んでいるため、非常に複雑なシステムで構成されています。
"楽器を作ることがゴールではなく、それを使うお客様が楽器を演奏して楽しみを得る、それを聴く方々がハッピーになれることが大事。"
Kenji Yamada
白土:しかし、シンセサイザーとインクジェット・プリンターのアーキテクチャーは非常に似ているので、システム全体を理解できるようになるまで、わずかな時間しかかかりませんでした。プリンター開発で培ったスキルを生かし、パフォーマンスを最大化するための改善ポイントを見つけた起動時間の短縮は、プリンターと電子楽器の両方に共通する課題です。プリンターは電源を入れたらすぐに印刷しなければならないし、電子楽器もすぐに演奏を始められるようにしなければなりません。そこで、起動時に大量の波形データをロードする時間を最小限に抑え、FANATOMの性能を最大限に引き出すことができました。
FANTOMに実装されているサンプラーも私が開発に携わりましたが、非常に興味深いものでした。CPUのリソースが制限される中で、最大限のパフォーマンスを発揮させることに非常に苦労しました。この苦労した経験がなければ、SP-404MKIIの開発に繋げることができなかったと思います。

音の中で夢を見る
将来の楽器に対する夢は何ですか?
山田 : ある程度の不器用さを持っていてほしい。あまりにも進化しすぎると人の入る余地がなくなってしまいます。楽器と人でお互いを補完し合うことで新しい何かが生まれてほしいです。
白土 : TR-808やTR-909がHouse/Techno、SP-404がLo-Fi Hip-Hopなどの音楽文化を創造・発展させていったように、楽器によって生み出される新たな音楽文化の創造と発展に、私が死ぬまで貢献し続けたいと考えています。
楽器から新たな音楽文化やジャンルが生まれ、そこからフィードバックを得て、楽器の技術がブラッシュアップされています。(例えば、SP-404からLo-Fi Hip-Hopカルチャー・コミュニティが誕生し、そこからフィードバックを得て、SP-404MKIIが誕生したように。)それらを繰り返すことで、楽器と音楽文化が進化し続け、音楽を愛する全ての人達の人生を豊かにしたいと考えています。