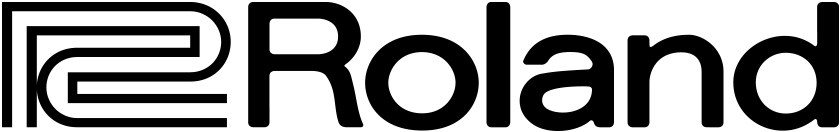「ローファイ・ビートで・・・」というトレンドは日本と強く結びついています。YouTubeやSpotifyには、スタジオジブリ風ビジュアルのローファイ・チャンネルやプレイリストがいくつも存在し、「勉強に集中」あるいは「リラックス」など、リスナーの場面に合わせて広く楽しまれています。インターネット上で生まれたこういった最新の流行に対し、数十年前からのローファイ・サウンド・ファンの中には異論を唱える人もいるかもしれません。ローファイ・サウンドが広く一般化していくことで、本来の音楽性のコアな部分が希薄になり、矮小化されたと感じている人も多いでしょう。しかしこれは一方で、若い世代の人たちがこのサウンドを知るきっかけになっている、という見方もできます。新たなファンたちは、日本のビート・カルチャーの歴史を掘り下げることで、本当のサウンドの魅力を味わうことができます。
新たなサウンドの登場:瀬葉淳と黎明期
卓越したプロデューサーでありビートメーカーでもあったNujabesこと瀬葉淳は、(J Dillaとともに)ローファイ・ムーブメントのゴッドファーザーと称されることがしばしばあります。自身のレーベル「Hydeout Productions」や渋谷の象徴であったGuiness Recordsを通して、誰よりも深く日本のビートシーンに貢献しました。
瀬葉は、渡辺信一郎監督による『サムライチャンプルー』(2004)のサウンドトラックを手がけます。これはジャズやソウルの雰囲気をまとったサウンドが日本のアニメにうまく融合された作品となりました。実際、Nujabesのタイムレスな音楽を初めて聴いた新しい世代の音楽ファンからも高い評価を得ています。それでも、Nujabesは、日本のビートメイキングの歴史に名を連ねたパイオニアの一人に過ぎません。日本の都心に今でも点在するレコード店には、この歴史を証言する無限の音源がしっかりと存在しています。そして、SP-404のような日本発の機材を使い、世界中のビートメーカーがビートを刻んでいます。こうして、「和の心」を内包した独自の表現が生まれました。80年代後半から、自宅で音源制作を行うプロデューサーやDJ、未来のカルチャーを象徴するアイコン的存在が、サンプルをベースにしたヒップホップを世界中のダンスフロアに解き放つようになりました。
「Jun Sebaが手がけた、渡辺信一郎作品『サムライチャンプルー』(2004)のサウンドトラックは、ジャズやソウルの雰囲気をまとったサウンドが日本のアニメにうまく融合された作品です」
日本が世界の舞台へ:Major Force、DJ Krushらの登場
1980年代後半に創設された音楽レーベル「Major Force」は、日本版ヒップホップのみならず、日本のダンスカルチャーの始まりを告げる存在でした。先見性に富んだ藤原ヒロシを中心に、高木完、工藤昌之、中西俊夫、屋敷豪太らが参加し、Major Forceはニューヨークやロンドン発祥のヒップホップやクラブミュージックを日本流にアレンジした一連の作品をリリースします。これらのレコードは、Major Forceにインスピレーションを与えた都市のレコード店に「逆輸入」されていきました。そして、その過程で、主要なトレンドセッターとのコラボレーションを次々と果たしていったのです。
その一人が、ポートベロー通りのレコード店、Honest Jon’sで働く、James Lavelleという名の店員でした。「Major Force」レーベルに触発されたこの新人店員は、その後90年代の伝説的なレコードレーベル「Mo Wax」を設立します。1993年に日本のヒップホップのコンピレーションを発表し、その翌年には、DJ Krushの代表作『Strictly Turntablized』がリリースされました。このアルバムは世界中の人々を驚嘆させ、日本がビートメイキングの中心として世界のステージに登場したことを示すものとなりました。
「Major Forceはニューヨークやロンドン発祥のヒップホップを日本流にアレンジした一連の作品をリリースしました」
アイデンティティの確立:FILE、Jazzy Sport、そしてその先へ
90年代半ばになると、世界中のレコード売り場の輸入盤コーナーには、数多くの日本人アーティストの名前が並ぶようになりました。いずれもサンプルベースのインストゥルメンタル・ビートを通じて、日本人のアイデンティティを確立することに貢献しており、元Deee-LiteのDJ、テイ・トウワによるボサノバ調のFuture Listening!から、INDOPEPSYCHICSの重くてムーディーなビート、RIOW ARAIの宇宙的実験に至るまで、多様な顔ぶれでした。ARAIは、昼間はゲームコンポーザーとして働きながらも、仕事が終わると様々なサブジャンルで活躍し、日本における電子音楽の境界線を切り拓いていきました。
コンピレーションのライセンスや輸入レコードといった流通ルートを通じて、一握りの日本人アーティストの名前が世に出ていった一方で、日本人DJ、ラッパー、ビートメーカーたちの活躍が見逃されていたことも事実です。彼らは東海岸で人気だったブーン・バップの影響を受け、日本国内の音楽シーンや日本のビートの未来を形作りました。日本のヒップホップ・レーベルの代表格であるFILE Recordsは、東京に拠点を置き、スチャダラパー、Rhymester、KING OF DIGGIN’のDJ MuroをフィーチャーしたMicrophone Pagerなどの結成に携わりました。FILE Recordsで重要な役割を果たした人物の一人に、レコード店Jazzy Sportの創設者である気仙太郎がいます。彼は、ヒップホップ・カルチャーが日本で爆発的に流行したこの時代、どのような影響を受けていたのかをこのように語っています。
「僕の場合、14歳のときにMalcolm McLarenのアルバム『Duck Rock』に夢中になったのが始まりでしたね。当時、ヒップホップに触れるには、もっぱら日本の雑誌か、ニューウェーブ系とアンダーグラウンド系の音楽をミックスして流していたFM局。当時はMajor Force一色。僕がそうだったように、日本人アーティストがヒップホップやDJカルチャーに反応しているのを見るのは、大きな意味があった。Major Forceの影響を受けた同年代の子も多かったと思う。その後、RhymesterやFILE Recordsから出た他のアーティストも登場した。僕がFILE Recordsを知ったのは、Major Forceを通してだった。というのも、FILEがMajor Forceのレコードを出していたから。ヒップホップだけでなく、日本のアングラ音楽全般を契約、リリースしていたので、当時の僕みたいな音楽好きには重要なレーベルだった」
Taro Kesen
サウンドのさらなる高みを目指して
90年代に入り、気仙太郎は語学習得と当時ロンドンで盛り上がりを見せていた音楽と文化の融合に身を委ねるべく、ロンドンに移り住みました。昼間はBlackmarket Records、Bluebird、Honest Jon’sなどのレコードショップで、夜はクラブで過ごしました。この行動により彼はHeavenで行われたRageやDingwallsでのHigh on Hope、The FridgeでのFunk、Soul、Rare Grooveといったクラブイベントや、Soul II Soul sound systemとの出会いを経験し、更に隙間を埋めるようにパイレーツ・ラジオからも多くを学びました。こうして、10年後に日本で最もアイコニックなレコードストアとレーベルの基礎が形づくられていったのです。
気仙は1995年に日本に戻り、FILE RecordsのA&R部門に所属しました。そこで、GAGLEと名乗るグループからデモテープを受け取ったことをきっかけに、Masaya Fantasistaと組み、2003年に新しいレーベル&レコードストアJazzy Sportが誕生しました。その後、日本のアンダーグラウンドミュージックの新たな時代を切り開くことになります。
「Jazzy Sportは、2003年に設立され、その後の日本のアンダーグラウンド・ミュージックの新しい時代を切り開いたレーベルである」

「僕たちはLaws Of Motion、Main Squeeze、Fondle‘Em、Stones Throwのようなインディーズ・レーベルに影響を受けたんだ。彼らは皆、いつもクオリティの高い音楽を出し続けていた。それで僕たちも音楽とスポーツの融合、すなわちレーベルのアイデンティティを探求するようになっていった。でもなんだかんだ言って、僕たちは自由なコンセプトを愛し、ボスを持たない。だから好きな音楽を出し続けられたんだ。」
Taro Kesen
お宝レコードの聖地
次に表舞台に姿を現したのは、DJ Mitsu The Beats、Grooveman Spot、そしてすべての始まりとなったGAGLE。そして世界を驚かせた、別次元を思わせるリミックス。Jazzy Sportのロゴはすぐに、「日本の新しいサウンド」を想起させるシンボルとなりました。これらはヒップホップとハウスの境界線、それは、当時数十年にわたってアフリカ系アメリカ人の音楽のステレオタイプとして渋谷の多くのレコード店の常識であった壁を打ち破りました。Gilles Peterson、Benji B、 Daniel Best、その他ヨーロッパの先駆的DJからの支持もあり、Jazzy Sportレーベルは世界への扉を開きました。この東京にあるレコード店は、世界を旅するこの業界の先駆者たちにとって重要な場所となり、彼らはここを訪れてはたくさんの日本の最先端のビートを持ち帰るようになりました。
Budamunkの伝説
Jazzy Sportのレガシーの一つとして名前が挙がるビートメーカーとして、Budamunkは欠かせません。日本の優れたビートメーカーとして世界にその名を轟かせる存在です。Tomonobu Kanno、通称Budamunkは日本で生まれ、1996年、16歳でLAに移住。そこで本格的にヒップホップにのめり込むようになりました。特に、若いころのKannoはA TRIBE CALLED QUESTや Slum Village、JayDeeやErick Sermonなどのプロダクションにのめり込んでいきました。
すぐに、彼は韻よりもビートそのものを追求するコミュニティに傾倒していきました。東部ハリウッドにあるLACCキャンパスで、Joe Stylesに会うようになっていました。Stylesもまた、彼らが愛したビートを作り出すマシン:MPCの実力を引き出すことに真剣になっていました。そして彼らはKeentokersを結成しました。Budamunkは振り返ります。

「MPCの使い方はよく知らなかったから、Joe Stylesから多くを学んだよ。実際、彼もよくわかっていなかったけど、ビートを作ることはできていた。彼はすごいビートを生み出してて、僕はそれを見て学んだ。もう一人のメンバーはLAID LOW。Chali 2naのブラザーで、Slum VillageのDJ Dezと仲が良かったので、LAID LOWとJoeは彼の家を訪れてはいろんなことを吸収し、後で僕に見せてくれた。こうやって学んでいったんだ。」
Budamunk

Budamunkはすぐに技術を習得し、LAのアンダーグラウンド界隈で気鋭のビートメーカーとして名が知れるようになりました。2005年、当時Jam Master Jay主催のScratch Academy MPCトーナメントで初めて優勝しました。しかし、LAアンダーグラウンドシーンに名が刻まれるようになったころ、USビザが切れたことによって東京に戻らざるを得なくなり、ゼロからの再スタートを強いられました。彼の帰国時、頭の片隅にあったのは、当時世界のアンダーグラウンド界隈で話題が沸騰していた、Jazzy Sportの評判でした。
「10年離れていたから、日本のヒップホップシーンについての知識はゼロ。でもJazzy SportのことはLAでも話題になっていたので知っていた。だから帰国してまず、彼らとつながることを目標にした。実際帰国してみると、彼らはものすごく知られた存在だった。彼らのイベントはいつも満員で、雰囲気も最高だった。彼らはいわゆるビートシーンが作り上げられる以前からビートを作っていたから、彼らこそが日本のヒップホップの新しいジャンルメーカーとしてふさわしいと思う。僕にとってはあれが日本のビートシーンの始まりだと思う。
Budamunk
流行の発信地
流行の発信地はJazzy Sportのレコード店でした。現在下北沢に移転しましたが、当時は世界一のレコード店密集地、渋谷の宇田川町にありました。そこには日本だけでなく海外からもマニアが訪れ、途切れることはありませんでした。Jazzy Sportはアンダーグラウンド・ミュージックの最もホットな場所の一つとして、名声を確立していきました。
そんな環境の中、日本のアーティストたちによって新たなプロジェクトが生まれていきました。2008年、BudamunkはついにJazzy sportsの成功を切り開くことになります。この時、拡大する日本のビートシーンの一部として、彼はISSUGIや5lackのような日本のアーティストと組むようになりました。こうして、日本のビートシーンの未来の礎が構築されていったのでした。
大阪のサウンド
2000年代半ば、東京におけるビートメイカー・コミュニティの中心には常にJazzy Sportがいました。同じ頃、大阪には独自のシーンが生まれつつありました。脈打つその心臓となったのは言わば目利きがキュレートする「セレクト・ショップ」ことLOSER。その運営者はアーティストでありDJであり、カルチャー・キュレーターでもあったMayumikiller。彼女は、2006年にLOSERを引き継ぐことになります。ちょうどLAから新しいプロデューサーやビートメイカーたちが特異なサウンドで興隆してきた頃でした。
やがてLOSERは、丁寧に選ばれたレコードやカセット、古着、その他あまたの音楽関連トレジャーが手に入る場所になっていきました。そして日本のオーディエンスに対し、LAの新しいビートシーンが、創造性を炸裂させているさまを紹介したのです。Mayumikillerにとってみれば、Flying Lotusのデビュー作「1983」と彼の最初のジャパン・ツアーこそが、日本独自のビートシーンにおいてワクワクする時代の幕開けでした。
「Flying Lotus の大阪初ライヴは、本当に大きなインパクトがあった。当時すでに日本のリスナーにはPrefuse 73とかMachinedrum、そしてもちろんJ-Dillaみたいなもっとエレクトロニックなインスト・ヒップホップを求めるファン層がいた。でもFlying Lotusがやっていたことは本当に突き抜けていて、日本の人たちもすごく注目した。Flying Lotusの日本初公演と、そのあと最初にBrainfeeder がRas G、Gaslamp Killer、Jon Wayne、Teebsといったアーティストを紹介したこと。これで日本のシーンの根底が変わった。私たちが今『日本のビートシーン』と呼んでいるものは、彼らLAアーティストがもたらしたインパクトから発達したと言っていいと思う。」
MayumiKILLER
Low End Theory: 新たなるハブ
LAから炸裂するようにあふれ出す創造力、その震源地にあったのは毎週開催されていたクラブイベント”Low End Theory”でした。そのファウンダーでありAlpha Pup Records レーベルを主宰していたDaddy Kevは、Nobody と D-Styleとともに膨大な数のアーティストたちをLow End Theoryにてキュレートしたのです。彼らアーティストたちは爆発的に創造力あふれる音をさらに外の次元へと押し広げ、じきにそれらは日本のオーディエンスにもなじみ深いものとなりました。やがて2008年から2015年にかけて “Low End Theory Japan” ツアーがほぼ四半期ごとに開催されるようになります。オーガナイズしたのは日本の音楽ジャーナリストであり、dublab.jpのファウンダー、原雅明。そこでまったく新鮮なものを目撃した感触を、彼は今でも覚えています。
「2008年にLAに雑誌の取材で行った時に見ました。ちょうど、Flying Lotusが出演していました。Warpからデビューする直前で、日本ではそれほど知られていない存在でしたが、LAでは既に人気がありました。彼も含めて、ビートメイカーが自分のビートを掛け合うBeat Invitationalが行われていて、ビートだけで、とても盛り上がっていたのが印象に残っています。 LAで実際に見たことと、また、Low End Theoryの主催者であるDaddy Kevにインタビューして聞いた話と、あとHashim Bharoochaという協力者もいたことで、日本でもLow End Theoryを開催したいと思いました。Kevに聞いた話というのは、LAでそれまでビートメイカーに焦点があたってこなかったのが、Low End Theoryが始まったことで状況が変わり、ビートメイカーに興味を持つ人が増え、また若いビートメイカーがどんどん登場するようになった、ということです。」
Masaaki Hara
そんな若いアーティストの一人にMtendere Mandowa すなわち レーベルBrainfeeder でのアーティスト名Teebsがいました。Teebsもまた原が日本で企画したLow End Theoryのツアーに参加。 LAで鍛え抜かれたサウンドを初めて日本に持ち込んだときの気持ちを、彼はこう振り返っています:

「本当にすごかった。正直、言葉が見つからない。ほんとうに人生が変わった。僕たちはLow End Theory サウンドを追求してきたわけだけど、僕たちがしていることに対して日本の皆が本当にそして深く関心を持っているそのさまは、もうクレイジーという他ない。すでにLow End Theory を数年やってきていたわけだけど、でもまだ結構アンダーグラウンドだったし。LAではあんな小さなスペースに本当に少人数が押し込められていたくらいだっていうのに、日本に来てみたら大手ヒットチャートに我々の名前が載ってるし、大きな会場でも完売状態。あのサウンドがこんなにも遠くにまで拡散したなんて、ただただ信じられない。」
Teebs
ひとたび日本の中に入ってみれば、東京の代官山にあるUNITや渋谷のWWWといったクラブで行われたパフォーマンスは、しびれるほど衝撃的ですらありました。それはLAアーティストの多くがまだ経験したこともないものだったのです。エネルギッシュな日本のオーディエンスが、最先端サウンドにどっぷり漬け込まれてしまったのだから。Teebsは彼の人生史上初の日本公演をはっきり覚えています。
「まだこれら大きな会場には慣れてなかったので、バンバンに満員なのを見て驚いた。Ras Gと Daddy Kevが立て続けに演り合って、オーディエンスからはワイルドなエネルギーが爆発。Nocando が僕のほうを向いて、僕はまだ結構若かったんだけど、彼の目が『次はお前の番だ』て言ってて、僕はもうガチガチに緊張してて。クレイジーな事態が勃発しつつある中その本当にてっぺんに自分が突っ立ってて、それがいかにイカれた状況か理解しはじめたという、その人生最初の時だ。僕は僕で最初のレコードを出そうって時だったから、自分が作ってきた一番お気に入りの音楽とともに準備は出来ていたけどね。そしてRas Gと僕と二人とも各々404を使った。そしてあの会場で自分がボタンを押して流れる音楽がどんだけでっかくて良い音で聞こえたか、衝撃を受けた。まさにワイルド。ほんとうに、ほんとうに、ワイルド。」
TEEBS

ピンときた瞬間
しかし、Low End Theory が公演したのはUNITなどの大きなハコだけではありません。各地方の拠点もさまざまな店内イベントやハプニングなどを起こしたのです。大阪の LOSERは、このシーン最高のパフォーマンスの多くを生み出すという重要な役割を果たしました。そこに名を連ねるのはDaedelus、Teebs、Ras G、MNDSGN、Machinedrum、などなど。そして過去、現在、未来にわたる日本のビートメイカー、その事実上ほとんどがLow End Theoryをはじめとするさまざまなショーを見に来ました。彼らが最も注目したのは、これらLAアーティストがセットの中で使っている機材でした。Mayumikillerは、そこで彼らが大好きなプロデューサーたちが、最新鋭の小さな日本のサンプラーから巨大なビートを脈動させるの見て、ピンと来た瞬間を覚えています。
「彼らが使っていたマシンが目立っていた。2000年代初めにビートメイカーたちが使っていたのはMPCだった。でも2009年~2010年以降はSP-404。Low End Theoryアーティストの多くにとって、海外公演はシンプルなセットアップで行いたいもの。SP-404ならとってもポータブルだからヨーロッパや日本へのツアーにも持っていける。特にRas GみたいにいつもツアーしていてめったにLAにいないような人にとって、SP-404はコンパクトで電池駆動できて、タフな存在。Low End Theoryライブショーに行くと、SP-404からのベースの音がどかんと来る。だからRas GやTeebsみたいな、日本人がほんとうにリスペクトしているようなアーティストがSP-404を使っているのを見て、皆それが忘れられなくなった。」
MayumiKILLER
「ショーが終わった後、オーディエンスが寄ってきてSP-404を見て『何を使っているの?コード線すら見当たらないね』って言ったのを今でも覚えている。RCA端子ケーブルだけだったからね。そしてこれがどれだけシンプルか見せてあげた。ツアーには完璧。小さいからどこにでも保管できる。違う国へ行っても電圧が違ってて回路が焼き切れないかどうかなんて心配しなくていい。単3電池が6本あれば済むし、そんなもの世界中どこにでもあるよね。まさに普遍的。」
Teebs
アンダーグラウンドで出来たつながり
この黄金時代に日本へやってきたアーティストの多くにとって、単に地元で鍛え上げたサウンドを聞かせるだけがツアーではありません。同時に日本のアンダーグラウンドで何が起きているのか観察することもできたのです。Teebsが、Daisuke Tanabeのような日本人アーティストを見たときの印象を思い出して語ってくれました。

「ツアーを通じて人脈ができたことこそが、本当に僕にとって大事なことだった。たとえばどこかで公演していて何人かとそこで出会ってその中の誰かが『あ、誰それをチェックしたほうが良いよ』と言ってくれる。そのおかげで僕たちはDaisukeみたいな人が公演しているのを見に行って、どれだけ彼がすごいのかを聴ける。もうまるで『よし、あんたは僕と同族だ。もうすでに分かってるよ。』っていう感じ。この人の音楽と精神とがまさに乗ってるからこそ、ずっとクールでいられる。そしてもし彼がLA在住だったら、もう今晩には日本へ向かって飛んで行ってるだろうよ。僕が言ってる意味、分かるだろ?」
Teebs
異国のビートメーカーやプロデューサーの多くには、たくさんのメリットがありました。こういったライブツアーで、多くのプロデューサーが一緒に複数のショーを掛け持ちするため、クラブや地元でのトレンドの垣根を超えて色々なアイデアが交換され融合される場面が生まれました。そしてそれぞれの個性を尊重することで、お互いの相乗効果や、新たな好奇心を高め合い、更にそれは生涯を通じたつながりを築きあげることになります。
「彼らから“Low End Theoryイベントに出演しないか?”と招待されたとき、最初はロサンゼルスのイベントだと思ってて、まさか逆だとは思いもよらなかった。そのイベントで彼らはゲストとかじゃなくて、自分たちがゲストだったんだ。Flying LotusやGaslamp Killer、またTOKiMONSTAにもインスパイアされたけど、中でもTeebsは最高だった。彼の繰り出すミュージックとアートは一貫性があったし、とにかくTeebsという人物像そのものがエッセンスとして確実に映し出されていた。彼の作品やパフォーマンスから自分自身を表現する事の美学を学んだ気がするよ。」
Daisuke
Ras Gの影響
Low End Theoryに出演するアーティスト達は、地元のビートメーカーにとっての憧れであり、様々なスタイルでコミュニティーに影響をもたらしました。中でも最も知られていたのは、他でもないRas Gでした。スタジオからライブパフォーマンスまでSP-404を使いこなすRas G は、彼の音楽、エネルギー、スキル、そしてその存在そのものが、2019年に亡くなるまで全世代のビートメーカーから高い評価を受け、そしてツアーで来日することで日本のオーディエンスにも深く影響を及ぼしました。その中の一人に、未来のSP-404開発リーダーとなる人物、白土健生が含まれていました。白土は、LAのSP-404コミュニティーの存在を耳にしており、実際に日本ツアーでそのパフォーマンスを目の当たりにした時のことを語ってくれました。

「私がSP-404の新たなコミュニティを意識し始めたのは2010年頃だったと思います。 当時、『remix』や『ele-king』といった日本の音楽雑誌がLow End TheoryやBrainfeederを特集し、それらの記事の中でSamiyam、Teebs、Ras G、TOKiMONSTAなど、SP-404を使っている海外アーティストの存在を知りました。 その当時、Low End Theoryは年に1-2回ほど日本でツアーをしていて、私は何度かそのイベントに足を運んでいました。中でも一番印象に残っているのは、2012年の代官山UNITでのRas Gのライブでした。中毒性のあるサイケデリックなビートに、Sun Raの楽曲からサンプリングした音が所々に散りばめられ、まるで宇宙空間にいるような感覚に陥りました。彼の神懸かったライブパフォーマンスの衝撃は、10年経った今でも私の脳裏に焼き付いています。」
Takeo Shirato

SP-404MKII開発者になるまでの物語
2000年代、学生だった白土は毎週のように地元(茨城県水戸市)にあるレコード店(Vinyl Machine)に通い、ダンスミュージックで使用されるサンプリングソースの知識を吸収することに生活の殆どの時間を費やしていました。また、日本の地方都市特有のジャンルレスなクラブカルチャーを体感することで様々な音楽から刺激を受けると共に、Stones Throw等のレコードレーベルや、EgonことEothen Alapattのような膨大な知識を有するレコード・コレクターに強い憧れを抱いていました。
その後、MadvillainのMadvillianyなどHip-Hopの金字塔となるアルバムがSP-303を中心に制作されていることを知った白土はSPのビートカルチャーに深くのめり込み、とうとう2017年にローランドに中途入社することになります。そしてその2年後、SNSや現実世界で広がるSPユーザーのコミュニティからのフィードバックを受け、SP-404MKIIの開発リーダーを担当することになりました。
2010年代、さらに世界に広まる日本のビート
2010年代、日本の若いビートメーカーたちの名声はますます世界に届くようになりました。Yosi Horikawa、Daisuke Tanabeのようなアーティストたちは、その比類ないグルーヴと日本的な繊細さを印象付けました。彼らの音楽は世界中の聴衆を魅了しました。東京では、中目黒Solfaや90 BPM Takeoverのような場所がLow End Theoryのスピリットでビートシーンを形作りました。そんな中で、Bugseed、Submerse、 Fumitake Tamuraのような才能にあふれたプロデューサーたちを発掘しました。日本のSP-404のコミュニティはオンラインでもリアルでも着実に広がりを見せていました。新世代のビートメーカーたちや愛好家たちにより、東京、京都、大阪などのシーンが育っていきました。
「2010年代を通して、日本の若いビートメーカーたちの名声は世界中に広がっていった」
そして今
Reo Matsumotoは多才なミュージシャンであり、ビートメーカーであり、ビートボクサーです。2019年、10年以上世界を飛び回ったのちに日本に戻った彼はどこか力強さがありました。17歳の時にビートボックスを習得し、ReoはWorld Beatbox Championshipsに日本代表として参加。その後旅に魅せられ、10年以上世界を旅していました。Reo Matsumotoはロンドン、ニューヨーク、メルボルン、など、その土地のミュージックシーンに溶け込みました。Gaslamp KillerやDIBIA$Eなどのビートメーカーに影響を受け、SP-404を手に入れました。そしてネットの世界で、世界のSP-404のコミュニティの中で名を馳せるようになりました。
日本に帰国して以来、彼は特にGoodfellas Tokyoを通して国内シーンで活発に活動しています。このブランドの目的は、いくつものクラブナイトやショーケースを通して次世代の日本のビートメイカーたちを紹介することにあります。

「自分たちのようなビートをつくっている人たちのためにGoodfellasを始めた。このイベントでポイントなのはDJ達ではなくてビートメイカーたち。もっと幅広いカルチャーから人々を呼び集めるというコンセプトでやった。ビデオグラファー、デザイナー、ダンサー、何が起きるかを見に皆が集まってくる。でもその中心にあったのは、いかにしてビートメイカーが一夜を盛り上げるかってこと。僕にとって東京は全世界のSP-404コミュニティの延長にある凄い存在。僕にはミュージシャンとしてのバックグラウンドがあって、どんな時でもたくさん即興でやりあったりするのが大好きだった。旅して、いろんな人に会って、一緒に演奏する。それが僕。だからSP-404を持って外に出て他のミュージシャンと一緒に楽しめる、他の機材ととも、他のSPとも、っていうのは僕にとっては最高なこと。」
Reo Matsumoto

ジャパニーズ・ビートシーンの最前線
日本のビートシーンをさらに広げようとするスピリットは全国各地で続いています。中目黒Solfaでのイベントから、京都のTable Beatsや大阪のLOSERに始まる地方でのクルーナイト、そしてGoodfellas Tokyo。もちろん先導するのはビッグネーム、でも新しいプロデューサーたちが常にすごい熱量で追い越そうとします。たとえばcell d break、Tajimahal、Green Assassin Dollar、そしてPhennel Koliander、或いは、Hermit City Recordingsなどの各種レーベル。それがなんであれ、独創的な日本のビートメイキング伝説はひたすら拡大しつづけるのみ、そのことに間違いありません。そしてそれとともにSP-404は、この世界で最もダイナミックでエキサイティングな音楽コミュニティのひとつ、その未来を形作る道具のひとつでありつづけることでしょう。