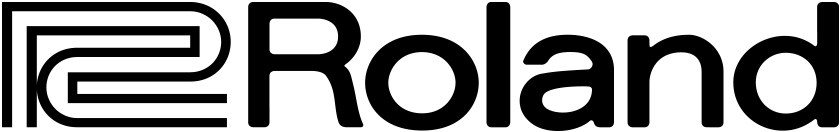Moodymannは、過去四半世紀を通して、一貫して最も優れたダンスミュージック・プロデューサーであると言っても過言ではありません。デトロイトの名門エレクトロニック・ミュージック・コミュニティから生まれたKenny Dixon Jr.は、1994年以来、主に自身のレーベルであるKDJ Recordsからダンスフロアを揺るがす名曲を次々とリリースしてきました。マスクやベールを被ってDJをすることが多いにもかかわらず、彼の顔がKDJ Recordsのロゴの一部であることや、ビデオゲーム「Grand Theft Auto」のアニメキャラクターとして登場することなどから、シーンで最も有名な人物の1人でもあります。

Three Chairsと2つのレーベル
サンプル・ベースプロデューサーでもライブ・ミュージシャンとしても、Dixonの温かみとうねりあるグルーヴは、Theo Parrish, Rick Wilhite, Marcellus Pittmanなど、才能あるプロデューサーが多数存在するデトロイトのハウス・ミュージックシーンを代表するものであり、彼ら全員がDixonと共にハウスのスーパーグループ「Three Chairs」を構成しています。
KDJは、Theo Parrish (1995年、”Lake Shore Drive”)、Rick Wilhite (1996年、“Soul Edge EP”)、DJ/プロデューサー/パーカッショニストのAndrés (1997年、“Trues EP”)による初期のレコードをリリースしましたが、それ以外は主にDixon自身の作品を扱ってきました。2002年には、姉妹レーベルのMahogani Musicを立ち上げ、ファンクキーボードの名手Amp FiddlerやソウルシンガーのMonica Blaire、エレクトロ/ヒップホップMCのSheefy McFly、同じくモーター・シティのMPCマスターであるJ Dillaの未発表アーカイブ素材など、Dixonの制作以外をリリースしています。
「KDJはまさにKenny Dixon Jr.そのものなんだ」とDixonは言います。「そしてMahogani Musicは世界のためのものなんだ。世界中の人々が手を伸ばし、彼らがこのレーベルにリーチする機会を与えてくれるんだ。」
「KDJはまさにKenny Dixon Jr.そのものなんだ。そしてMahogani Musicは世界のためのものなんだ。」
独立性を保つ
1990年代初頭のDixonの最初の作品は、地元のラップクルーのためのHIPHOPトラックで、Dixonはアルバムのカバー写真には出ていましたが、クレジットには彼の名前はありませんでした。「スタジオのお金を払った人は誰でも『プロデューサー』だった」とDixonは言います。「彼らはその功績を得たし、すべての出版権も手に入れた、これも私たちは何も知らなかったんだ。でも、当時はそれだけ酷かったということ。まったく、私たちは子供だったんだ。」
Dixonは、今後の作品でそのような経験を繰り返さないと決意し、「今回は自分の名前を掲載して欲しい」と告げます。そして彼は、黒人オーナーのビジネスの独立維持を約束し、長年の友人から成るチームをスタッフとして頼っています。
「彼らは私と共に育ったんだ」と彼は語ります。「そして私は彼らを信頼している。なぜ他のいけ好かない奴らの子供たちは大学に通ってるんだ、私の周りの仲間が苦労しているのに、私は彼らをその状況から救い出せる。彼らはPRのやり方、マネジメントの方法、弁護士のたわごとだって学ぶことができる。彼らは読み書きができ、愚かではないんだ。でも、私が彼らに教えられないのは、信頼だよ。」

「スタジオのお金を払った人は誰でも『プロデューサー』だった。彼らはその功績を得たし、すべての出版権も手に入れた、でも私たちは何も知らなかったんだ。」
Skating on Soul
KDJ/Mahoganiのクルーは、半年に一度のメモリアルな週末の間にデトロイトで開催する、Soul Skateパーティーの監修を手伝ってくれています。このパーティーは、世界中のローラースケート愛好家を魅了し、この10年間で一夜限りのイベントから、ダウンタウンで開催される毎年恒例のMovement Festivalに対するユニークでファンキーなカウンタープログラムの1週間へと成長しました。
KDJ Recordsの起源は1994年にさかのぼりますが、レーベルの最初のリリースとなると少し曖昧です。「KDJ 1」としてクレジットされているのは、Dixonの名前でリリースされたEP『Moody Trax』と、Moodymannの名前でリリースされた12インチ『I Like It』/『Emotional Content』の2枚で、Dixonはプレス工場での取り違えによるものだと考えています。
希少性の理由
どちらのリリースも、レーベルの多くの作品と同様に希少価値があり、コレクターの間では高値で取引されています。Dixonは、そのような希少性は市場の混乱を意図したものではないと主張しています。「最初は、150枚のレコードをプレスする余裕しかなかったんだ。でも今は3000枚、4000枚くらいはできるかもしれない。私はただそれらが売れることを確認したいだけで、何も得られないのは嫌なんだ。その送料は私が払わなきゃいけないしね、あれは面倒だよ。レコードを作るにはお金がかかるし、私にはそういうものを保管するスペースがないんだ。」
1996年に発売された『KDJ 6』は、Dixonの初期の珠玉の2曲をフィーチャーしています。「I Can’t Kick This Feelin When It Hits」は、Chicの「I Want Your Love」から「What am I Gonna Do, Gonna Do, Gonna Do?」のボーカル・サンプルを使用し、抑制された緊張感とカタルシス的な解放感を感じる、たまらなく爽快なアンセムに変わり、「Music People」はMass Productionの「Welcome to Our World (Of Merry Music)」を使用して、Moodymann独特の怪しげな雰囲気をリスナーに届けます。
「最初は、150枚のレコードをプレスする余裕しかなかったんだ。でも今は3000枚、4000枚くらいはできるかもしれない。私はただそれらが売れることを確認したいだけで、何も得られないのは嫌なんだ。」
ビッグ・ドロップ
Dixonのハウストラックは、彼のデトロイト仲間のトラックと同様に、ディスコ、ファンク、R&Bだけでなく、モーター・シティのテクノシーンのハイテック・ソウルからも影響を受けています。「当時のテクノはもっとソウルフルだった」Dixonは言います。「四つ打ちである必要なんてないし、それが重要ではないんだ。とにかくいい感じだったし、トラック全体が美しかった」
彼は最近、違和感を抱いています。「最近では、彼らはドロップ(曲やアルバムのリリース)ばかりを欲しがっている。それは何も悪いことではないが、私たちは常にドロップしていた」とDixonは言います。「誰もドロップの方法を教えてくれなくても待つ必要なんてなかった。私たちはイカれた夜をずっと楽しんでいた。一晩中ビッグ・ドロップだったんだ。」
当初、DixonはKDJから12インチのシングルとEPのみを出し、アルバムのリリースをまとめるために他のレーベルにトラックのライセンス契約をしていました。1997年にCarl Craigのレーベル、Planet EからリリースされたデビューLP『Silentintroduction』には、KDJの初期のシングルの多くが収録され、その後10年間で最高のレコードの1枚であり続ける傑作となりました。その後、イギリスのレーベルPeacefrogから、1998年の『Mahogany Brown』、2000年の『Forevernevermore』、2003年の『Silence in the Secret Garden』、2004年の『Black Mahogani』と4枚のアルバムをリリースしました。しかし、それからDixonはフルレングスのリリースを主に社内で行っています(ただし、2012年のScion Audio/Visualの『Picture This』と2016年の!K7の『DJ-Kicks』は例外です)。
「当時のテクノはもっとソウルフルだった。4つ打ちである必要なんてないし、それが重要ではないんだ。とにかくいい感じだったよ」
Analog Down the Street
Dixonの作品は、ビンテージ・ヴァイナル特有のスナップ、クラックル、ポップ、そしてオールドスクールな楽器のダスティで霞みがかったサウンドですぐにそれとわかります。「僕は最高の技術を持っているわけじゃない。まだストリートで分析しているんだ」と彼は説明しています。「できるだけ隠そうとはしているけど、それでも霧がかかってあたたかい音が出てくる。なぜかはわからない。80年代と同じ機材を今も使っているからかもしれないし、それが問題かもしれない。まだ多くの点でアップグレードしていないだけだよ」
彼の機材には限界があるようにも思われますが、Dixonは実に幅広いスタイルやムードの仕事をしています。例えば「Shades of Jae」は、Marvin Gayeの「Come Get to This」の1977年のロンドン・コンサート・バージョンと、Bob Jamesの「Spunky」のキーボードの華やかさをブレンドして、スタッターなストンプに仕上げています。
また、ラウンジ・ジャズのライブ演奏である「Long Hot Sex Nights」(元Frank Zappのサイドミュージシャンで、Dixonと頻繁にコラボレートしているサックス奏者のNorma Jean Bellをフィーチャー)もあります。「Technology Stole My Vinyl」のファンクアップなフュージョン、「Dem Young Sconies」のミニマル・アシッド、「The Thief Who Stole My Sad Days … Ya Blessin’ Me」の感動的なゴスペル、そして、ブルースマンの元祖Muddy Watersをサンプリングした「Sunday Hotel」のルーツなグラインドなど、挙げればきりがありません。
「私は最高の技術を持っているわけじゃない。まだストリートで分析しているんだ」
パープル・インフルエンス
そしてもちろん、Dixonの主なインスピレーションであるPrince Rogers Nelsonの影響もあります。悪名高い「Freeki Mutha F cker」は、Princeの影響が最もあからさまに表れています。2003年にホワイトレーベルとしてプレスされ、2011年まで正式にリリースされませんでしたが、常にリクエストの多いライブの定番でした。2007年のMovement Festivalでのライブの前に、Dixonはデトロイト警察から「Freeki Mutha F cker」を演奏しないよう警告されました。警察は明らかに、その下品な言葉がモーター・シティをエロティック・シティに変えてしまうのではないかと心配していました。
天候や技術的な問題でライブが予定より大幅に遅れ、Dixonはもう1曲しか演奏する時間がないという知らせを受けたため、予定されていたセットリストを取りやめ、とにかく「Freeki Mutha F cker」を演奏することにしました。「ふと見回すと、彼らはステージの上にいたんだ」とDixonは警官について語っています。「でも、後ろには誰もいなかったので、ステージの後ろから逃げたよ」その後、彼は待機していた車に飛び乗り、ジェファーソン・アベニューを夜の中へと消えていきました。
Princeへの愛情の表れとして、過去15年ほどのDixonのアルバム、特に2014年の『Moodymann』、2018年の『Sinner』、2020年の『Taken Away』では、彼自身のボーカルが目立つようにフィーチャーされており、その音楽はしばしばバックミュージシャンによってライブで演奏されています。これは彼のサンプル・ベースの作業が進化したかのように見えるかもしれませんが、Dixonは彼の作業プロセスは根本的に変わっていないと主張しています。彼はサンプラーを相変わらず、―しばしばリラクゼーションの一つとして―使っていると語っていますが、それは彼が「気持ちの赴くままの感覚」でのトラックをより多くリリースするようになったからなのです。
「ふと見回すと、彼らはステージの上にいたんだ。でも、後ろには誰もいなかったので、ステージの後ろから逃げたよ」
Golden Ticket
DixonはKDJのリリースをめったに再プレスしません – リリースしたプレスがなくなる頃には、彼の気持ちは次に移っています – しかし、何度か新しいエディションに異なるトラックを含めて、再プレスすること(例えば、1995年の EP『Inspirations From a Small Black Church on the Eastside of Detroit 』のリイシューのように)はありましたが、コレクター間の混乱と需要を高めることになります。時には、アルバムの中に未発表のホワイトレーベルの12インチを入れたり、遊び心でWilly WonkaのGolden Ticketのアナログ盤を購入者にプレゼントすることさえあります。
このレーベルは、今でも必見のブランドですが、実際にアナログ盤を入手するのは難しいようです。 例えば、『Sinner』は基本的にDixonの裏庭で開かれたBBQでしか入手できなかったですし、Snoop Doggがゲスト出演した2018年のアルバムは、レーベルのオフィスから出ることすらありませんでした。Discogsでの販売価格は平均で$500.00にも高騰しています。
Dixonは、この現状を実際には自分の試みをふいにしようとした結果だと説明しています。このレコードがホワイトレーベルとしてプレスされる頃には、彼はそのサウンドにすっかり飽き飽きしていました。「嫌だった」「それが残酷な真実だ」と彼は認めています。しかし、その頃にはすでにレコードはプレスされ、梱包されていたため、彼には不要となったレコードが何箱も残っていました。「こいつらをどうするか?」Dixonは言います。「みんなを座らせて、ランダムに配るだけだよ」
「多くの人が、実際に創作をする代わりに、創作について学ぶことに多くの時間を費やしている。でも新しい何かが出てくるたびに学ぶよりも、楽しむことに時間を費やしたいんだ」
Slow Down
KDJの立ち上げから30年が経った今でも、Dixonの活動は衰える気配を見せていません(2020年のアルバム『Taken Away』には「Slow Down」というタイトルの官能的なジャムが収録されています)。彼は、自分が長年に渡り活動できているのは、個人的な哲学によるものだと考えています。
「多くの人が、実際に創作をする代わりに、創作について学ぶことに多くの時間を費やしている」とDixonは言います。「新しいテクノロジーはあっという間に登場し、誰もが新しいテクノロジーに飛びつきたがる。新しいものに飛びつくと、本当に自分のやりたいアートワークをする機会がなくなるんだ、なぜなら学んでいるだけだからね。まあ、学びたくない、ただ作りたいだけのこともある。テーブルの上に鎮座している、このつまらないものを学んでる時間なんてないんだ。そんなことやってられない。新しい何かが出てくるたびに学ぶよりも、楽しむことに時間を費やしたいんだ」